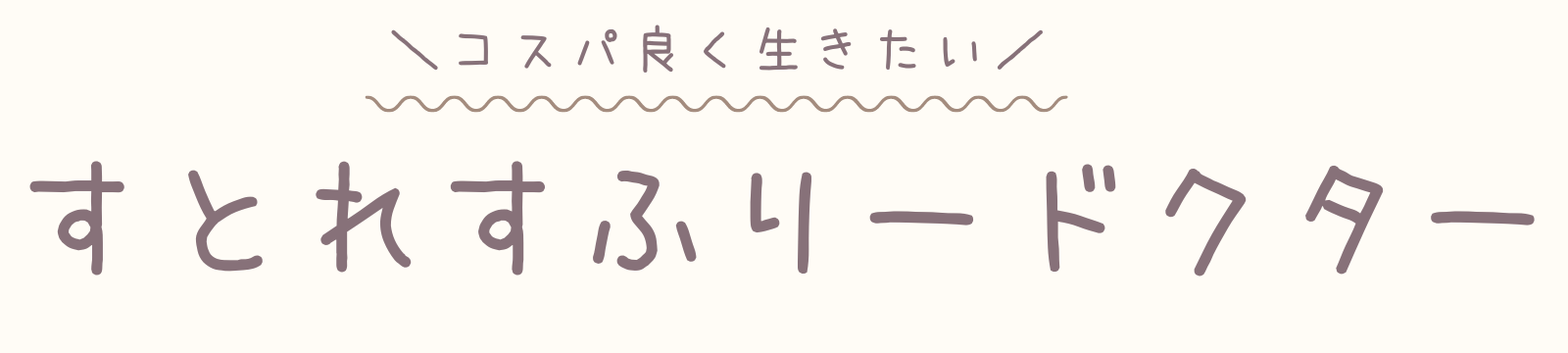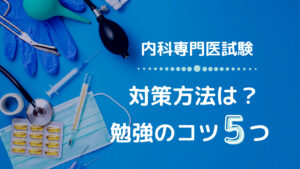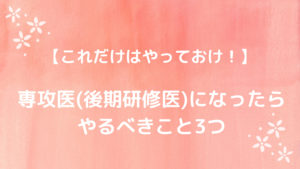4月から晴れて研修医デビューという方も多いのではないでしょうか。
CBT、OSCE、ポリクリ、国試をパスしやっと社会人に…!とはいえ右も左もわからずこの二年で何を学べば良いの?と路頭に迷っている人も多いはず。
この記事ではそんな迷える初期研修医のためにやっておくべきことや学んでおくべきことを解説します!
この記事を書いた人

医局に属さない働き方をするアラサー女医。医局を辞めたい若手医師のサポートを100件以上行ってきました!
この経験を活かして【医局の辞め方・バイトの始め方】をお伝えしていきます。
医師の初期臨床研修とは
医師国家試験に合格後一人前の医師になるために、2年間各科をローテートし、研修をします。これが初期研修です。
この2年を終えると臨床研修修了証が付与され、晴れて一人で保健診療を行えるようになります。
この2年間は医師としていろんなことを吸収し、成長ができるかなり貴重な期間。
後悔しないためにやっておくべきことがあります。
後悔しない!初期研修医のうちにやっておくべき7つのこと
①多くの手技を経験
初期研修医のうちにいろんな科の手技を学んでおくことは必須です。
採血、ルート確保、尿カテを入れる、胃管を入れる、挿管、CVなどなど。初めての手技はどんなものでも1回はやってみた方が良いでしょう。
三年目以降になると各々自分が選択した科に進むことになります。例えば私は麻酔科ですが、一旦麻酔科に進むと他の科のことは正直よくわからなくなります。血液内科で教えてもらった骨髄穿刺や神経内科で教えてもらった髄液検査の測定、呼吸器内科で教えてもらった胸管ドレーンも今となってはよくわかりません。
ただ、研修医の時に経験させてもらったことでなんとなくこんな手技だったとか、これに気をつけた方が良いとか今後に役立つことが身につきます。その少しの差が将来自分が何かしら対応しなければならない時に生きてきたりします。そういった経験ができるのは初期研修医の間だけです。
できる限り手技は経験しておきましょう!
学んだ手技はバイトでも役立つ
三年目以降になると医師バイトができるようになります。
その際にも採血やルート確保、尿カテくらいはできた方が良いです。
できることでバイトの幅も広がるので今のうちに身につけておきましょう!
②救急対応
研修医が一番活躍できるのが救急外来です。
救急ローテも必須ですし、日直や当直でERにいる時間も多いでしょう。walk inや救急車対応をしていると必然的にファーストタッチの能力が身につきます。このファーストタッチではどんな疾患を疑うか、どんな検査をオーダーするか、何科にコンサルするかなど一連の流れを叩き込むことが重要です。
正直、専門性の高い治療や処方はできなくてもいいんです。なぜならそれは各科が行うことだから。医師全員に求められるのはそう言った細分化した技量ではなく、今目の前にいる患者さんを適切な科へ繋ぐこと。
だからこそ、そのパイプである初期対応ができるように、救急では積極的に対応を学びに行きましょう。
救急で経験したことが後期研修医以降も役立つ!
専攻医になると自分で主治医をやったり上級医として当直を任されたりします。
「いざという時頼れるのは自分だけ!」という状況になる可能性も。ある程度救急対応を身につけておけば怖い思いをしなくて済みますよ。
最初は辛いですが頑張りましょう!
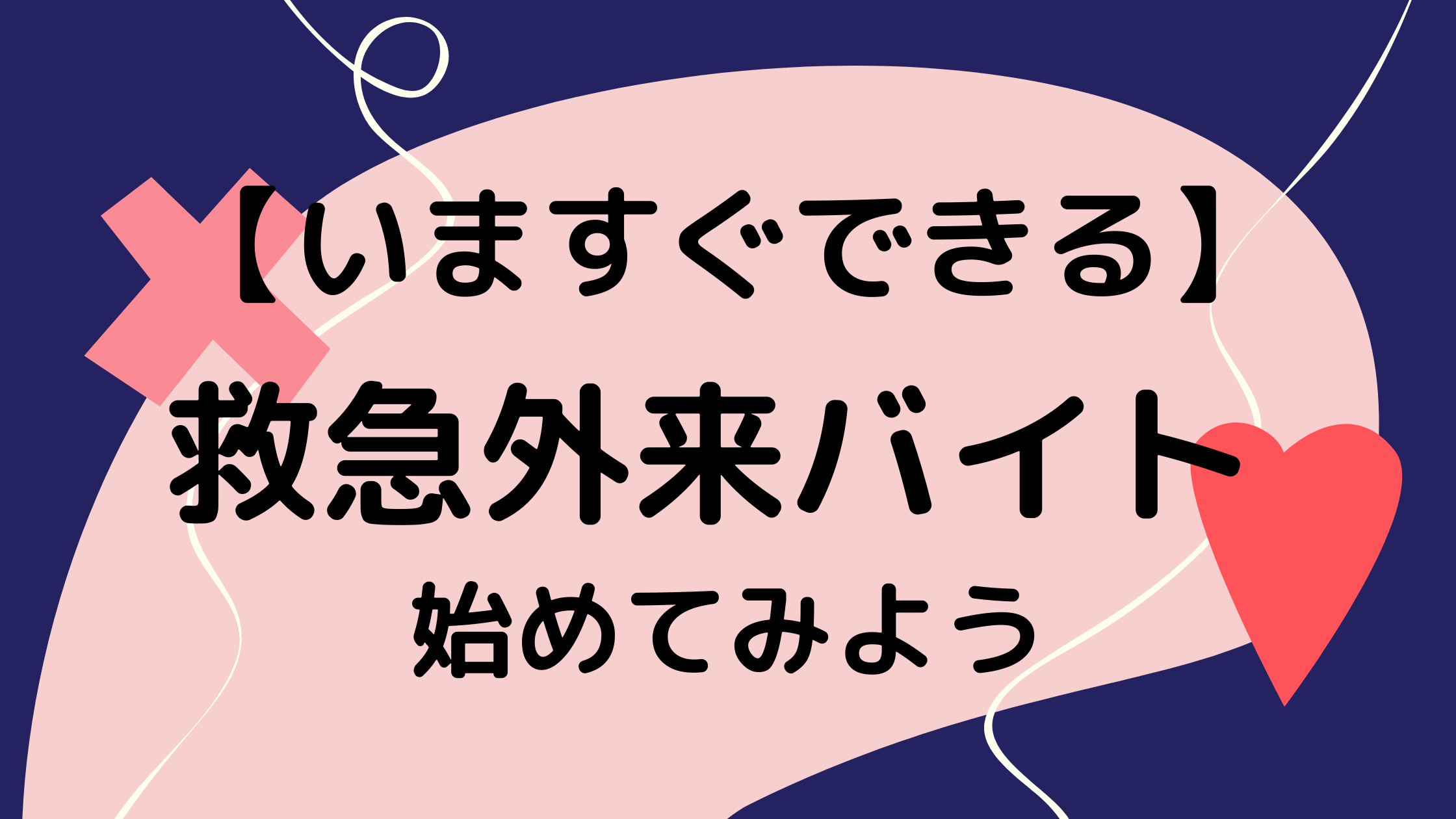
③common diseaseに慣れる
医師として一番出会うことが多いのがcommon diseaseです。
国試でやったようなマイナーな遺伝子変異とか希少な疾患は専門病院でないと担当しません。ほとんどが肺炎、尿路感染、胃腸炎などcommon diseaseです。担当する症例の多くがこういった「よくある病気」だからこそ、これらの対応を覚えておけばまず困りません。
咳、痰、のどの痛み、発熱、腹痛、下痢や吐き気、血尿、頭痛、めまいそれぞれの検査オーダー、治療法、入院期間など覚えておきましょう!
④人との繋がり
多くの人と繋がれるのも研修医の特権です。
スーパーローテートで複数の科を回るからこそいろんな職種や各科の先生たちと顔見知りに慣れます。残念ながら後期研修以降は自分の科に属してしまうため人間関係がかなり狭くなります。
私は麻酔科ですので、麻酔科Dr、オペ看護師、外科の先生くらいしか院内で話すことはありません。ですが、初期研修の間は科の垣根を超えて働くことができますし、そこで知り合いを多く作っておくと今後の人生で助けてもらえることが多くなります。
例えばコンサルするほどでもないけれど、専門科の先生の意見をチラっと聞きたい…なんてこと、診療をしていれば山ほどあります。そんな時も「この症例ってどう思う?」みたいに気軽に聞くことができます。これは本当にありがたいです。
自分の将来を助けると思ってできる限り人との繋がりを作っておきましょう。
⑤後期研修先の情報収集
この前初期研修のマッチングを受けたばかりなのにもう?と思うかもしれませんが、後期研修先を決めるのはかなり早いです。
- 一年目のうちに医局・病院をリサーチ
- 二年目の4〜5月にいくつかに絞る
- 5〜6月に病院見学の申し込み
- 6〜7月に見学に行き第一志望を決定
- 8月に内定をもらう
このくらいのスピード感で進んでいきます。
つまり一年目のうちから動き出さなくてはいけないということです。初期研修の時と違ってマッチングではなく、自ら病院見学にいき入職したい意思を伝える→内定をもらうという流れなので自発的に動かないと進みません。
出回っている情報もかなり少ないですし、実際に働いている人に聞いてみないと知らないこともたくさんあります。早いうちからリサーチだけでも初めておきましょう。後期研修は初期より長く、専門医の取得にも関わります。
先輩、後輩、研修医の同期、大学の同級生、高校の同級生、オーベンの伝手など使えるものはなんでも使って調べましょう!
⑥産業医資格を取る
初期研修医のうちに取れる資格は数少なく、専門医やサブスぺは後期研修を受けないと取れません。
ですが、持っている資格は「医師免許」のみで将来大丈夫だろうか?と不安に思うこともありますよね。そんな人におすすめなのが産業医の資格です。指定の講習を受けるだけで取れます。試験や臨床勤務年数○年以上といった縛りもありません。
 りん先生
りん先生私も取得しました!
実際に産業医として働くことは今の所していませんが、今後のライフスタイルや進路を決める時に1つの選択肢として持っておけることがとても安心材料になっています。
後期研修で病んだ時も安心!
初期研修以上に後期研修では精神を病んだり体力的にキツかったりします。ドロップアウトする人も多いです。
そんな時に「なんの資格もないのにこれからどうしよう…」と悩みたくないですよね。でも産業医の資格を持っていれば「産業医になったっていいし大丈夫だ!」と思えます。何かあった時の退路を持っておくことは本当に本当に心強いです。(自分も何度助けられたかわからない笑)
今後どんな人生になってもなんとかなるし大丈夫だ!と思えるように資格は取っておいた方が良いでしょう
\たった6日間で産業医の資格を取る方法/


⑦オンライン診療研修を受けておく
コロナ禍を期にオンライン診療のクリニックやバイト先が増えています。
オンライン診療をするには厚生労働省のオンライン診療研修を修了することが必須となっています。私自身も受けて修了証を発行しました。一度受けるだけで一生更新なしでOKです!
無料で受けられるのでぜひ研修医の間に受けておきましょう。


後期研修先によっては必須の場合も
私の友人の病院では入職までにオンライン診療研修を受けて修了証のコピーを提出するように言われていました。
その病院では今後オンライン診療を普及させていく計画があるからだそうです。後期研修に入るギリギリだと各書類集めやら引っ越しやらでバタつきます。
あらかじめやっておくと焦らず済むので可能な限り前倒しで取得しておきましょう!
オンライン診療のバイトができるようになる
今はオンライン診療のバイト募集が多く出ています。
一般内科で風邪薬を出したり、自由診療でAGAやダイエット外来をやったり。自宅で働けるのも大きなメリットです。
保険診療・自費診療問わずたくさん募集があるのでぜひ取得しておきましょう。


【番外編】各種書類をスキャンしておく
初期研修が終わるといろんな書類を関係各所に送る機会が増えます。後期研修先、医局、外勤先、バイト先などなど…。
大体必要な書類は一緒なので一気にスキャンしドライブやスマホに保存しておくと良いですよ。
- 医師免許証
- 保険医登録票
- マイナンバーカード
- 臨床研修修了証
- 履歴書
- オンライン診療研修修了証
- 銀行口座のわかるもの
特に医師免許は大きいし嵩張るのでスキャンして持っておくと便利です!
コピーの提出を求められることも多いのでA4で印刷して家に何枚かおいておくとより良いです。



ぜひ参考にしてくださいね
バイトの応募は複数サイトで見比べて効率的に!
初期研修の間はバイト禁止ですが、研修終了後の後期研修医になるといろんな医師バイトに応募できます。
今は当直1回2万円とかでやっていると思いますが、バイトの場合当直1回10万円以上なことも珍しくありません。寝て過ごすだけのいわゆる寝当直の場合、本当に寝ているだけで3万円もらえることも。
効率的に稼げるようになるのでぜひバイトを始めましょう。特に始めのうちは紹介サイトを見比べて初心者向けの案件や脱毛・健診バイトから始めると失敗しません。
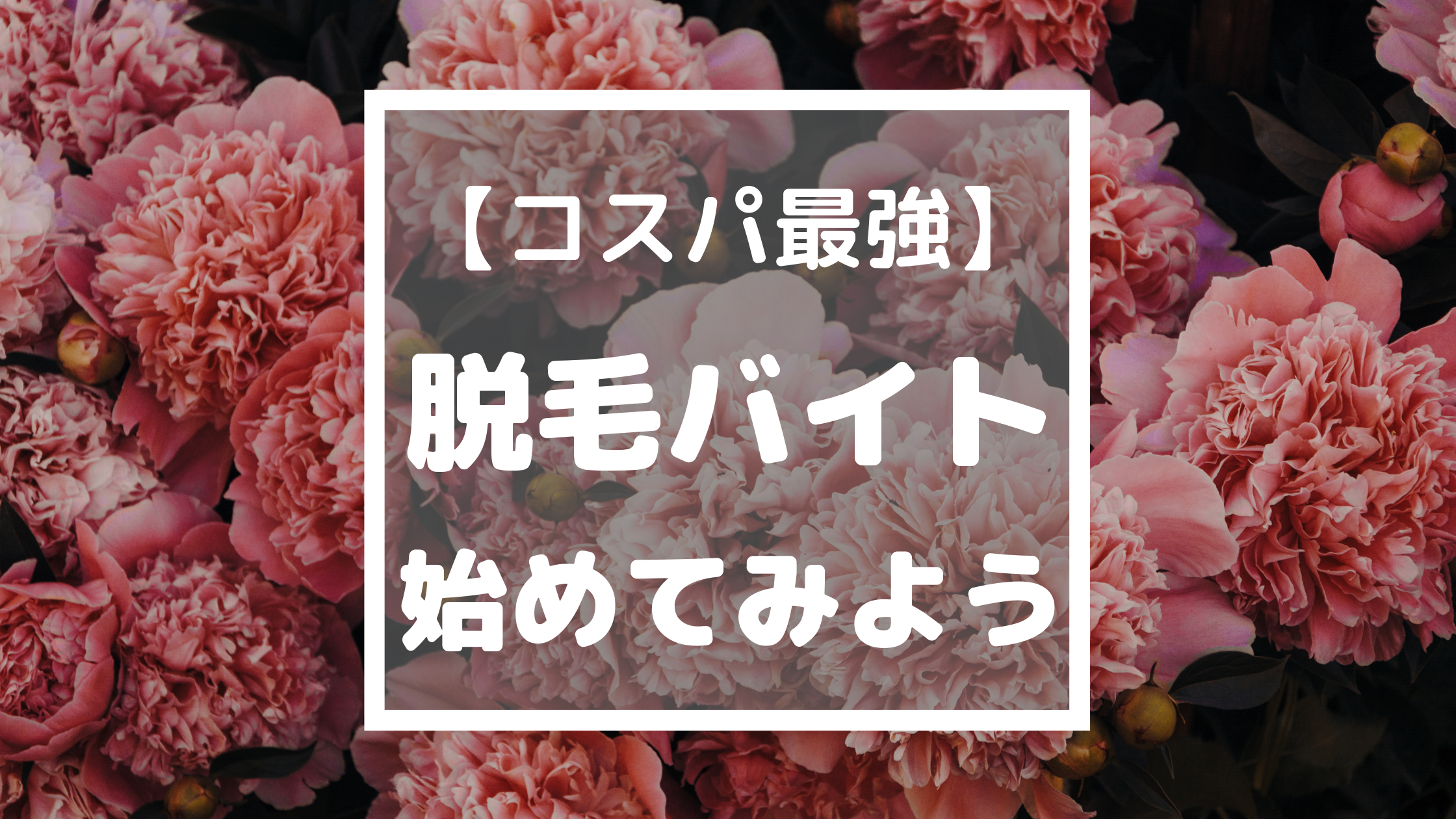
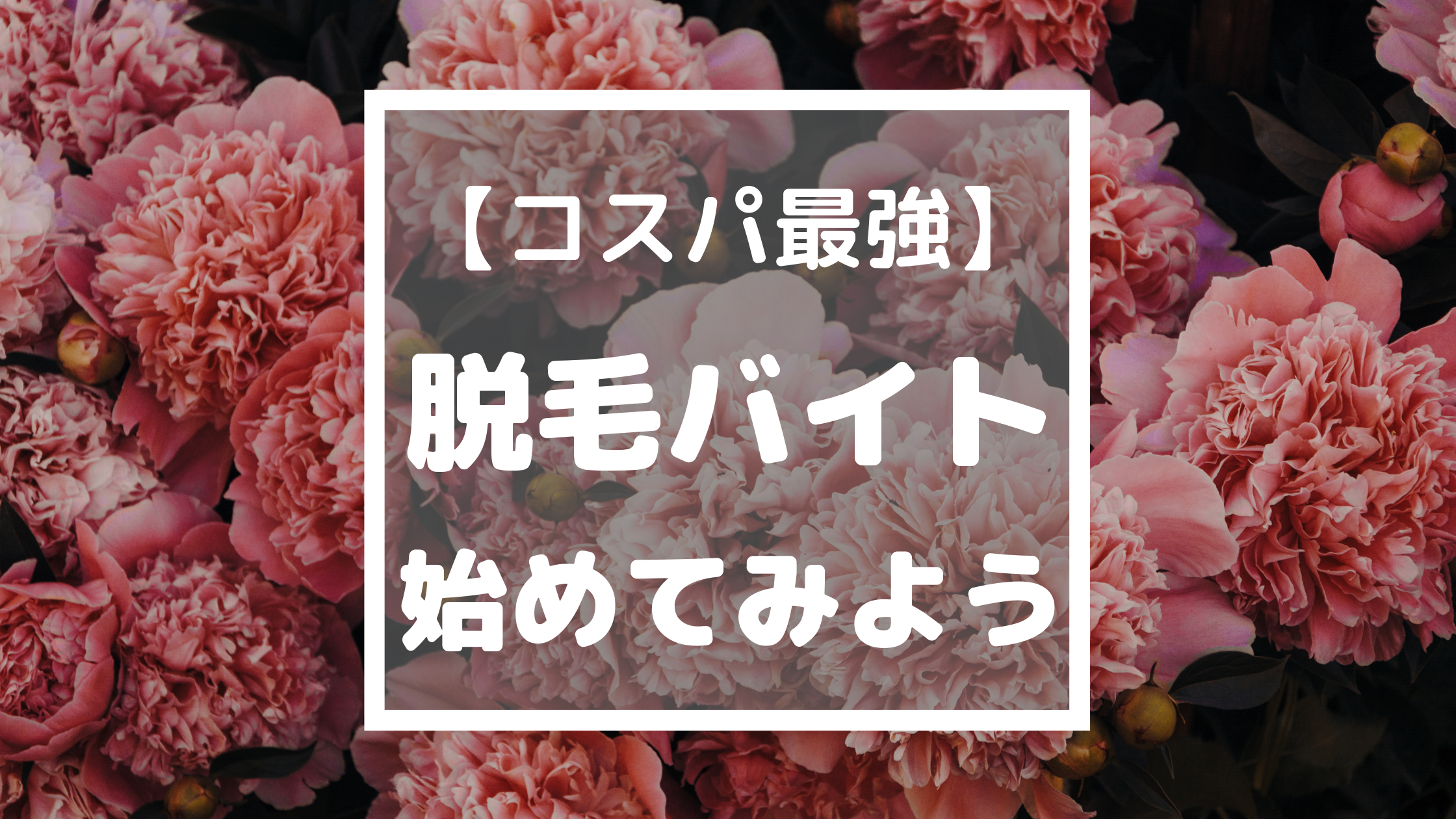
\ 医師バイトで効率よく稼ぐ /
初期研修でやっておくべきことまとめ
初期研修はたった二年ですが、この期間にどう過ごすかでその後の医師人生に大きな差ができます。
やれる手技は積極的に経験し、救急で初期対応を学ぶ。そして資格を取ったり人脈を形成したりして将来の進路を確固たるものにしていきましょう!
楽しい2年間になるよう応援しています。